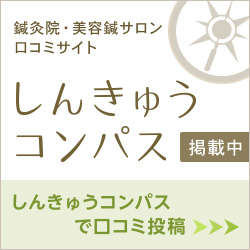ブログ(全て)
漢方薬と鍼灸の違いと役割分担
鍼灸治療と漢方薬の違いと役割分担

東洋医学は、数千年の歴史を持つ伝統的な医療体系であり、その中核をなすのが鍼灸治療と漢方薬です。
これらはどちらも、単に症状を抑えるのではなく、体の内側からバランスを整え、自然治癒力を高めることを目的としています。
私たちの体は、西洋医学が臓器や部位ごとに細分化して捉えるのに対し、東洋医学では「気」「血」「水」といった概念や「陰陽五行」の考え方に基づき、全身のつながりや調和を重視します。
このホリスティックな視点こそが、鍼灸と漢方薬が多くの慢性的な不調や難病に対して有効とされる理由です。
今回は、鍼灸と漢方薬の違いと役割を説明し、両者をどう使っていくかについて書いてみます。
漢方薬の特徴と効果

漢方薬は、植物や鉱物などの天然素材を使い、体質や症状に応じて調合される薬です。… 全文を読む
眼圧を下げるツボ
眼圧を下げるセルフケア

眼球の内側の圧力を調整する液体は、常に一定の圧力を保ちながら循環しています。
この圧力こそが「眼圧」と呼ばれるものです。
眼圧は低すぎても高すぎても、目の健康にとって好ましくありません。
とくに、眼圧が高すぎる状態が続くと、眼の奥にある視神経が圧迫を受け、視機能に重大な障害を引き起こす可能性があります。
眼圧が高い状態、特に急激な眼圧上昇や長期間にわたる高眼圧は、視神経に深刻なダメージを与えます。
視神経は、目で見た情報を脳に伝える重要な役割を担っています。
この視神経が損傷を受けると、視野が狭くなったり、視野の一部が欠けて見えなくなったりする「緑内障」を発症するリスクが高まります。… 全文を読む
鍼灸の会報誌に寄稿したハナシ
三旗塾

鍼灸の勉強会・三旗塾に、昔からお世話になっています。
鍼灸学生の頃に勉強会に参加するようになり、北海道や静岡県にいて参加できない時期もありましたが、かれこれ通算25年ほど。
代表の金子先生の講義に惚れて勉強会に参加し始め、その後もご無沙汰していた時期があるにもかかわらず、何か機会があるごとに誘いの声をかけていただき、その気持ちが本当に嬉しくここまできました。
ご縁だなぁと思っています。
数年前は、東京穴性研究会という新プロジェクトの勉強会に誘っていただき企画から数年ご一緒させていただきました。
そこで鍼灸師の仲間もでき、楽しくも充実する時間を過ごせました。
基本的には組織でワイワイやるよりひとりで気ままにやるタイプなので、今でも独学で生きています。… 全文を読む
乳がん術後のリンパ浮腫のむくみを鍼灸で減らせるという研究
乳がん術後のリンパ浮腫が鍼灸で改善

乳がんという大きな病気と闘いながら、しかもリンパ浮腫という不安にも対応しなければいけないことは大変な負担かと思います。
鍼灸がそこでお役に立てる…という話を書きます。
リンパ浮腫とは
乳がん治療のひとつに手術があります。
リンパ節転移が有ると、腫瘍だけでなくわきの下のリンパ節手術(腋窩リンパ節郭清)を受けることとなります。
腋窩リンパ節郭清の一般的な副作用のひとつは、腕のリンパ浮腫(腕の浮腫)です。
腋窩(わきの下)のリンパ節を切除すると、手術後に体の老廃物を運ぶリンパの流れが悪くなり、手術した側の腕に溜まり腫れることがあります。… 全文を読む
妊婦さんで腰痛でお悩みの方へ
妊娠中の腰痛に対する鍼灸が73%に効いた報告

腰痛は多くの妊婦さんが経験すると言われています。
原因は「ホルモンの作用(骨盤が開きやすくなる)」「体形や姿勢の変化」「下半身の血行不良」などが考えられます。
ホルモンのはたらきによる骨盤のゆるみの影響で、妊娠4週~15週頃の早い時期から腰痛が起きることがあります。
また妊娠28週~32週頃には、体形の変化や下半身の血行不良が関係する腰痛も増加するようです。
このように妊娠期には腰痛がつきものですが、その悩みに鍼灸で対応できるのではないかという研究をご紹介します。
『妊娠中の腰痛に対する鍼治療』
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29482798… 全文を読む
コロナ後遺症と鍼灸治療
コロナ後遺症でお悩みの方へ

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染が拡大し、多くの方が罹患されました。
感染自体は治癒したものの、その後も様々な症状に悩まされる「後遺症」に苦しんでいる方が少なくありません。
倦怠感、記憶力低下、頭痛、咳、呼吸困難、関節痛、筋肉痛、不眠、乾燥肌、脱毛、嗅覚・味覚障害など、その症状は多岐に渡り、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。
とくに、疲労感や「ブレインフォグ」と呼ばれる思考力・集中力の低下、脱毛、味覚・嗅覚障害などは、メディアでも取り上げられることが多く、多くの方が不安を感じていることでしょう。
令和3年5月末時点の東京都病院経営本部のデータによると、
嗅覚異常:32%
倦怠感:27%… 全文を読む
不妊ストレスに効くツボ
不妊治療のストレスに効果的なツボ

妊活は、喜びと期待に満ちた道のりであるはずですが、同時に大きな不安やストレスを伴うことも少なくありません。
「赤ちゃんを望んでいるのに授からない」「周囲の妊娠報告に焦りを感じる」といった経験は、多くの女性の心を揺さぶります。
実際、不妊治療を受ける方の半数以上に軽度のうつ症状が見られるという調査結果もあります。
今回は、不妊治療とメンタルヘルスの密接な関係について掘り下げ、東洋医学(鍼灸)の視点からメンタルを安定させるのに役立つツボをご紹介いたします。
不妊治療を受ける半数に軽度うつ症状

不妊治療は、いつ結果が出るかわからない、終わりが見えないマラソンのようです。… 全文を読む
イライラしやすい人に効くツボ
イライラに効くツボ

日々の生活でストレスが溜まると、どうしてもイライラしがちになりますよね。
仕事、家庭、人間関係…、現代社会はストレスの種で溢れていると言っても過言ではありません。
今回は、イライラの原因を東洋医学の視点から紐解き、ご自身でできるセルフケアと、当鍼灸院で行っている施術について解説いたします。
そもそもストレスとは
ストレスとは、外部から心身に加わる刺激によって生じる緊張状態のことです。
不安や悩みといった精神的なものだけでなく、暑さ寒さといった気候の変化、病気や睡眠不足、仕事の忙しさなど、日常生活で起こる様々な出来事がストレスの原因となります。
進学、結婚、昇進といった喜ばしい出来事も、環境の変化に伴う適応が必要となるため、ストレスの原因となることがあります。… 全文を読む
何となく落ち着かない時のツボ
何となく落ち着かない…慢性のイライラに効くツボ

心が何となく落ち着かない時ってありますよね。
とくに原因となるようなはっきりしたものもなく、心の病気というほど大げさでもないけれど、何となく心ここにあらずのような、モヤモヤとした日々…。
仕事に集中できなかったり、趣味を楽しめなかったり、日常生活に支障が出てしまうこともあるかもしれません。
これ、実は「慢性のイライラ」が原因かもしれません。
弱いイライラや気づまりが常時あることで、知らず知らずに何となく落ち着かないという症状になるのです。
神経が過敏になっている方に多く、イライラしやすかったり、夜中に何度も目が覚めてしまう、些細なことで動揺してしまうなどの症状を伴うこともあります。
鍼灸院で施術をしていると、このようなお悩みを抱えた方が思いのほか多くいらっしゃいます。… 全文を読む
肩こりに効くツボ
肩こりに効くツボ

肩が凝るのは、肩にある筋肉からの悲鳴です。
首から肩にかけての筋肉には、無数の血管が張り巡らされており、血液を通して筋肉は酸素や栄養を受け取っています。
しかし、長時間のデスクワークや猫背などの不良姿勢、運動不足などによって肩の筋肉に負担がかかると、筋肉は硬くこわばり、血管を圧迫して血行不良を引き起こします。
すると、筋肉に蓄積した疲労物質は排出されず、必要な栄養も行き届かなくなり、肩のこりや重だるさといった不快な症状が現れます。
さらに、こりが筋肉の緊張を増長し、血行を悪化させるという悪循環に陥ってしまうのです。
この悪循環を断ち切り、滞った血液の流れを改善することで、肩こりの症状は緩和されます。
今回は、肩こりの根本原因である血行不良に着目し、改善のためのセルフケアのツボをご紹介します。… 全文を読む